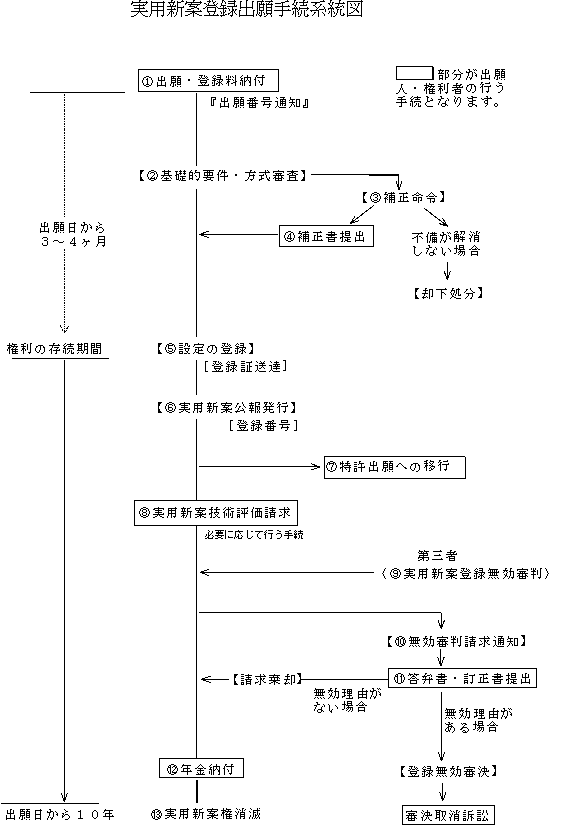 |
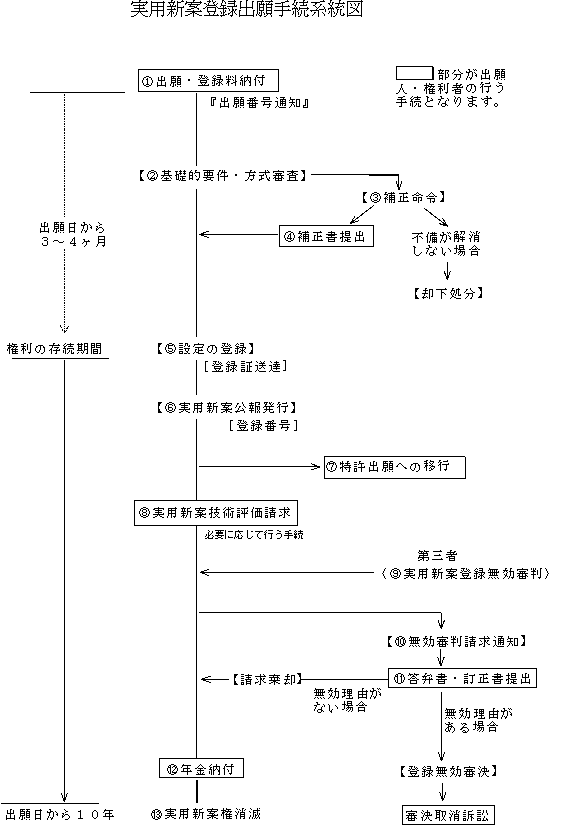 |
| (H22.1.1現在) ①特許庁への電子出願が完了しますと、オンラインで出願番号通知が参ります。その後の審査についての応答は、全てこの『出願番号』によって行われます。なお、出願人は、出願時に第1~第3年分までの登録料を一括納付することが必要です。 ②実用新案登録出願では、特許出願と異なり、新規性、進歩性等の実体審査(内容審査)は行われず、基礎的要件審査および方式審査のみが行われます。基礎的要件審査では、出願内容が物品の形状等の登録対象であるか否か、公序良俗に反するか否か等が審査されます。方式審査では、様式、手数料等のチェックが行われます。 ③基礎的要件または方式要件に不備があった場合、特許庁より『手続指令書』によって補正の指示がなされます。 ④出願人は、『手続補正指令書』発送の日から30日以内に補正書を提出し、不備を解消することができます。不備が解消されない場合、出願が却下されます。 ⑤基礎的要件および方式要件を満たしている場合、特許庁の登録原簿に設定の登録が行われ、実用新案権が発生します。その後、実用新案登録証が交付されます。 ⑥実用新案権の登録日から2ヶ月程度経った後、明細書・図面等を記載した実用新案公報が発行され、権利内容が第三者に公開されます。なお、実用新案登録出願は、特許出願に比べ早期(3~4ヶ月程度)で登録されるため、登録前の出願公開制度は採用されていません。 ⑦実用新案登録出願から3年以内であれば、設定登録後であってもその登録内容について特許出願を行うことができます(実用新案から特許への移行)。実用新案権が設定登録された後に実体審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に利用することができます。 ⑧実用新案登録出願は、新規性、進歩性等の実体的要件を審査することなく、設定登録の処分がなされます(⑤)。このため、本来登録されるべきでない技術が登録される場合も生じます。そこで、何人も、特許庁に対し、出願中の考案または登録実用新案に関する技術的な評価(実用新案技術評価書)を請求することができます。 一方、実用新案権者は、他人に対して権利行使する場合には、実用新案技術評価書を提示した警告を行わなければなりません。 ⑨実用新案権に対して何人も登録無効の審判請求を行うことができます。特許庁による登録処分の適否を判断するため、公衆に意見を求める制度です。 ⑩実用新案登録無効の審判請求があった場合、請求人の主張する無効理由を記載した書類が実用新案権者に届きます。 ⑪実用新案登録無効の審判請求に対しては、答弁書により反論することが可能です。また、必要に応じて訂正書を提出することより権利内容を訂正することもできます。 ⑫第4年分以後の登録料は、前年以前に納付することが必要です。数年分又は全期間分を一括で納付することも可能です。登録料の納付がない場合、実用新案権は消滅します(⑬)。 ⑬実用新案権は、設定の登録(⑤)により発生し、その存続期間は、出願日から10年で満了します。実用新案権の満了後は、何人も自由にその考案を実施することができます。 |